白亜のホールに少女の魂が吹き荒れる
 |  |
白亜のホールに少女の魂が吹き荒れる つねに賞賛と非難のあいだを往復しているFiona Apple。 彼女は、第3ミレニアムのエネルギーに満ちたロックであり、1930-40年代風のささやくジャズ歌手であり、言葉の名匠の座を約束されたシンガーソングライターである。 4月29日、ロサンジェルスにある瀟洒なウィルターン劇場は眉をひそめるほど音質がこもっていたが、その障害を乗り越えて、彼女は観客を満足させるコンサートを行なった(最高ではなかったとしても)。 残念なことに、2200席あるこの会場の音響再生は標準以下だったので、「Criminal」「Sleep To Dream」「On The Bound」のようなロックの推進力は殺がれていたし、彼女がジャズ風に自由なリズムで歌う「Love Ridden」や「Limp」の一部などからは親近感が伝わってこなかった。 そのせいで、いつもなら重低音を響かせるバンドのベースとドラム(CDでは一貫して強力なパンチを効かせている)は、まったく無力だった。各楽器の音は区別がつかないほど混じりあっていて、どの楽器が前面に出てどんな微妙な演奏をしようと、その多くは虚空に吸い込まれていくようだった。 それは一種の療法のようだった。彼女は毒舌を吐くたび、深呼吸をして、勢いをつけて次の曲の演奏を始めた。かつてテニスのJohn McEnroeがグランドスラムの決勝戦で行っていたように、おそらく気持ちを爆発させることは、次に行うべきことに集中すべくストレスを解放するための手段なのだろう。強烈なサーヴを打つか、新たな確信を持ってロックするかの違いはあっても。 ラヴェンダー色の丸首長袖Tシャツと足首までの腰布を着けたAppleは、現在MTVの目玉になっている「Fast As You Can」を歌う前にも、そうやって気持ちを集中して6人編成のバンドを引っ張っていった。カミナリのようなオルガンの轟音を引き継いで歌へ、そしてアラベスク風のギターソロへ続いたこの日のヴァージョンは、観客を興奮させた。 ブラックライトを浴びて雰囲気が整うと、ジャズを愛する歌手Fiona Appleが前面に現れた。「Paper Bag」ではドラマーのMatt Chamberlainがブラシングを器用にこなし、テクニック抜群のKeith Loveは「I Know」でアップライトベースを演奏した。 アンコールの拍手に応えて、Appleはひとりで舞台に現れた。彼女の頭上に漂うスモークは羽毛のように見えた。会場には、Cole Porterが1930年に歌った古いジャズ「Just One Of Those Things」の、引っかき傷だらけのレコードの音が流れていた。
かつては「My Descent Into Madness」「It's A Motherf--kr」「Going To Your Funeral」「Electro-Shock Blues」など陰鬱で終末的な曲を書いていたアーティストが、この夜は観客を楽しませるほうの役割についたのは、ひとつの皮肉だった。それはいわば、激烈なAppleの嵐の前の静けさだったのだ。 by Scott Taylor |
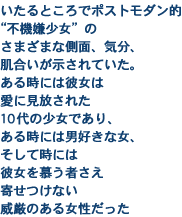 Appleはこの日も思い出したようにカンシャクを起こしては、しばしば聞き取れない悪態を吐いていた。印象に残ったのは、その内容がこの日のひどい音響についてではなく、個人的な些細な事柄だった点である。
Appleはこの日も思い出したようにカンシャクを起こしては、しばしば聞き取れない悪態を吐いていた。印象に残ったのは、その内容がこの日のひどい音響についてではなく、個人的な些細な事柄だった点である。 この日は、
この日は、