この国では何をやっても攻撃される。まったく馬鹿げているよ!


queensrycheのgeoff tate(ヴォーカル)、scott rockenfield(ドラム)、michaelwilton(ギター)は、自分たちが今でもプログレッシヴメタル運動の闘士であると感じるかと聞かれて、目を白黒させんばかりだ。tateは答える。
「とんでもない。それは他の人間の意見であって、僕らの意見じゃないよ」。
wiltonがさらに言う。
「楽器を演奏できるというだけで、そうしたくくりに入れられてしまうんだ。僕らは演奏の上手なミュージシャンというだけだよ」。
tateもすぐにこう指摘する。
「ジャーナリストは誰かが付けたレッテルやカテゴリーを受け入れている。そんなことする必要なんてないんだ。そいつは他人のルールであって、そんなものの仲間なっちゃいけない」
3人ともtateの陽気に切り捨てるような言い方に笑い出したが、これは核心を突いたポイントだ。グループ名をタイトルにした'83年の4曲入りデビューepを、自主レーベル206recordsからリリースして6万枚を超えるセールスを記録し、capitol-emiとの契約にこぎつけてからというもの、このシアトル出身の5人組グループは、ヘヴィメタルの領域を広げるためだけでなく、体制側は何が良いことなのか知っている、という観念に戦いを挑むためにも努力してきた。『ragefor order』、有名なコンセプトディスク『operation: mindcrime』、200万枚を超えるクロスオーヴァーヒット『empire』などのアルバムで、このグループはまさしくそれを行った。その原動力となったのは、壮大なギターハーモニー、推進力のあるリズムセクション、tateによるダイナミックで奔放な歌いっぷりだ。
queensrycheの最新アルバム『q2k』…このタイトルは、大流行になっているミレニアムの頭文字に引っかけたものであることは一目でわかるが、queensrycheが自分たち自身の第2章を新たに始めたことも指している。これはatlanticrecords移籍後初めてのアルバムであると同時に、ギタリストで曲作りにも貢献していたchrisdegarmo抜きで作った最初のアルバムでもある。これによって、以前の所属レーベルemiamericaの解散に始まる激動期は終わりを告げることになる。
rockenfieldがその時の事情を振り返る。「あれは奇妙だったな。前のレコード(『hearin the now frontier』)に伴うツアーを'97年の夏の間に行う予定だった。後でわかったことだが、emiは会社を解散しようとしていたんだ。それもなんとレコードの発売前から。僕らは知らされていなかったけど、ツアーに入る1週間前に業務を停止したため、ツアーはどこからも実質的な支援を受けられない状態で、宙に浮いてしまった。宙に浮いたのはレコードも同じだ。結局ツアーは'97年の秋に行った。そして次のレコード作りに入ろうという矢先に電話がかかってきて、chrisが脱退すると知らされた。(あれは)一夜にして情勢が一変するという感じだった。一寸先は闇とはあのことだよ」
degarmoの脱退はスムーズにはいかなかった。「僕らは南米ツアーをやらなければならなかった」とwiltonは説明する。「あのときはたいへんだった。(脱退のことは)発表していたけど、契約の関係でこのツアーをやらなければならなかった。そこで南米まで行ってファンの前で演奏したんだけど、あれは見せかけの演奏だった。悲しかったよ。chrisと一緒にバンドとして演奏するのはあれが最後だった」
degarmoが脱退してからのバンドはショック状態だったが、rockenfieldは「今振り返れば、僕らにとって驚くべきことが起こった」と言う。まもなく理想的な交替メンバーが見つかった。プロデューサーでギタリストのkellygrayだ。彼は、tateがqueensryche加入前に在籍していたmythというバンドで、一緒に演奏していた人物だ。grayは確かに『q2k』で存在感を発揮している。こんな言い方をすると3人はたじろぐが、このアルバムには、queensrycheの前のアルバムにあったグランジギターの名残がいくらか残っているが、現代っぽさを維持しつつも昔のサウンドを呼び戻している。全体的には、さらにグルーヴ主体のサウンドになっていて、“burningman”と“falling down”では、rockenfieldは広まっていきそうなリズムをたたき出している。『empire』のように聴いてすぐインパクトを与えるようなものではないかもしれないが、繰り返し聴いていくうちにわかってくる良さがたくさんある。
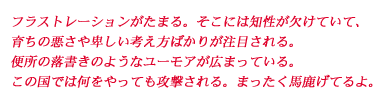
tateは言う「僕らがこれまで演奏してきた曲のほとんどは、メンバーがそれぞれ1人で作ったものだ。バンドで実際に曲を演奏するのは、ツアーのリハーサルに入るときが初めてだった。だがこのアルバムはすべてライヴ演奏だ。曲のジャム、手直し、レコーディングを同時に行った。ごく自然に生まれたという感じだね」
wiltonはこう言う。「とても楽しかったよ。うんざりするようなことがなかったから。無理なくやった、ただそれだけだ。必要以上にリハーサルをやったり、考え過ぎたりはしたくなかった。今は昔に戻って、どんな感じでやったのかを把握して、それぞれのパートを覚え直さなきゃいけないんだ」。新曲を覚える必要もあるが、grayの場合はさらに、差し迫った劇場を回るツアーに備えて、昔の曲を覚えなければならない。ツアーの詳細なスケジュールはまだ公表されていない。
これまでのqueensrycheのアルバムに収録されていた曲の詞は、社会や政治といったテーマを突き詰めることがよくあったが、『q2k』収録曲には、もっと個人的なものを歌う傾向がある。“burningman”は、ネヴァダ州レノの郊外で毎年開催されている砂漠祭に触発された曲だ。人々はその祭に行って、社会のルールを捨て、長めの週末休暇を自分たちだけで乗り切ろうとする。これがtateをとらえたコンセプトだ。他の曲は「僕らが去年置かれていた状況を歌ったものだ」と、tateは思い起こす。「裏切りとか、友達をなくすこととか、人生をやり直すこととかね」
queensrycheはこれまでどおり、セックス、ドラッグ、ロックンロールというお題目を唱えるのではなく、本道を突き進んでいる。tateは次のように不平をもらす。「フラストレーションがたまる。そこには知性が欠けていて、育ちの悪さや卑しい考え方ばかりが注目される。便所の落書きのようなユーモアが広まっている。この国では何をやっても攻撃される。自分が気に入ってもいなくても、何かを作り出した人には、僕は敬意を表するよ。なぜだかわかるかい?その人は何かをやったんだよ。ただ存在しているだけじゃなくてね。何かを作って、僕らの社会に付け加えているんだ。それによって、何らかの点で誰かが恩恵をこうむる。それなのに、どんなことについても、新しいことをやった人を世間は引き裂くんだ。まったく馬鹿げてるよ。成功をつかんでお金を稼いだら、ジェラシーで頭に血を上らせて、みんなが足を引っ張ろうとするのさ」
tateは自分が何のことを話しているのかわかっている。彼のバンドの名前は今でもファンにとって意味のあるものだが、その知名度は最近落ちてきている。'80年代にメインストリームの主役でありながら、'90年代に消えていったアーティストは数多いが、queensrycheのメンバーも、そうしたアーティストと同じように、メディアの反発という残酷なとげを感じてきた。しかしそれを気に病んではいない。tateは言う。「他の人間がどう考えているかを気にしていたら、フラストレーションがたまるだけだ。そのことを肝に銘じていれば、ちゃんと乗り切れるよ」
by bryan_reesman