【インタビュー】内田直孝、逆境に立ち向かって成長したことに気付けるソロ・シングル「Adversity is the first path to truth.」

Rhythmic Toy Worldのヴォーカル・ギター、内田直孝が4月3日に初のソロ・シングル「Adversity is the first path to truth.」を、Rhythmic Toy Worldの4thミニ・アルバム『PLACE』と同時発売した。リリース発表と同時に公開された内田のブログには、メジャーレーベルを離れ、「STROKE RECORDS」に戻りインディーズでの活動を開始することへの思いが、ファンへのメッセージとして長文で綴られていた。今再び原点に戻って音楽を届けることについて、ソロ作品について。BARKSでは初となる単独インタビューは、リラックスし饒舌に話す素顔の内田が印象的に残る取材となった。
■ソロを出すという発想はなかったです
■いつか作品として残したいなとは思っていたんですけど
――改めて、インディーズ・レーベルからRhythmic Toy World、ソロの2作品をリリースした今の率直なお気持ちを聞かせてください。
内田直孝(以下、内田):バンドの方は、1枚目の『軌道上に不備は無し』を出したときの気持ちで制作をしようというのが、テーマとしてありました。誰も自分たちを知らない状態で、作品を聴いてライヴに来てくれるかどうかというところをすごく意識したんです。出来上がってみて、それはできたんじゃないかって思いますし、自分たちの中では快心の出来です。ちょうど、昨日がインストア・イベントだったんですけど、前のフルアルバムのときよりもお客さんが来てくれていましたし、反応も良かったんです。僕らがどこでやるか、誰と一緒にやるか、どういうことをやるかということではなくて、お客さんがもっともっと近くに感じたい、というところがRhythmic Toy Worldには求められているんだなって。そういう確信と自信は感じました。やっぱり、「これでよかったのかな、大丈夫かな」という不安はあったので。
――大丈夫かな、というのは自分たちの選択が間違っていないかどうかということ?
内田:そうですね。(インディーズでの活動では)自分たちの選択が、どこまで行っても自分たちのエゴ的なことから発信するわけで。それが、求められていることとズレていたらさみしいなというのはあったんです。2月に書いた僕のブログでは、言わなくていいことまでさらけ出したんですけど、その結果、それ以上のものが今返ってきてるなって。結局、またみんなからもらっちゃってるなっていう感じです(笑)。
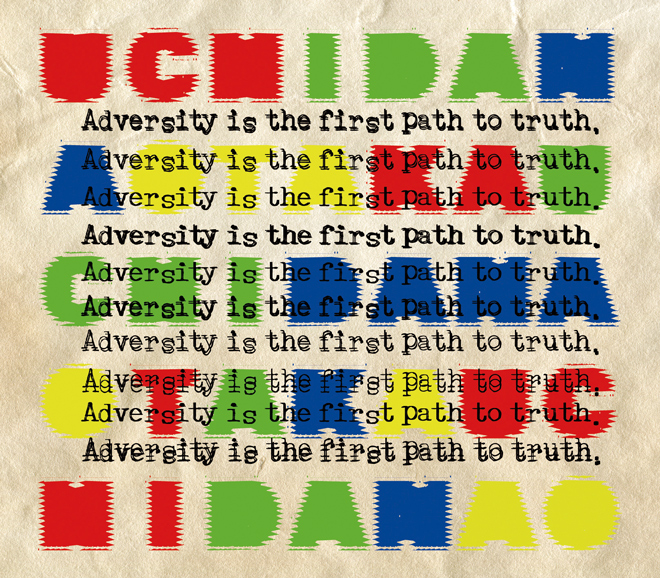
――今回、内田さんがソロ・シングルを出すと聞いて、バンドのイメージが強い分、正直驚きました。
内田:ね!?僕もですよ。
――というと、ソロ作品を出すという発想はこれまでなかったわけですか。
内田:ソロを出すという発想はなかったです。まあ、弾き語りの活動のためだけに新曲を書いたりとかはしていて、ライヴでもやっていたので、発売するというよりは、いつか作品として残したいなとは思っていたんですけど。
――バンド作品と同時発売になったのはどうしてですか。
内田:バラバラで出すより、2枚同時に華々しく出した方が面白い。それとRhythmic Toy Worldというバンドと内田直孝というヴォーカリストは、決して別ではなくて1つだっていうところも表現したかったんじゃないかなと思うんです。僕が発売日を決めたわけでないんですけど、同時発売になったときに僕はそう受け止めました。いつも4人でやっているものがソロで1人になるという不安やさみしさもありましたし、そういう気持ちを汲んでくれたのかなって思っています。
――弾き語りでやってきた曲たちの中で、この3曲を収録した理由はありますか。
内田: 今回の3曲はソロ活動をする上で、歌作りの面白さを改めて感じさせてくれた曲たちで、だいたい全部2日くらいで作った曲なんです。そのときの衝動で書いたというか。
――ギターを持って歌って、そのまま出来た感じ?
内田:全部そんな感じでした。1曲目の「電影少女」は、ちょうどクリスマス付近にあった弾き語りのイベントの前に、クリスマスだしラブソングっぽい新曲が書きたいなと思っていて。でも普通のラブソングじゃ面白くないので、アニメキャラに向けてラブソングを書いたら、僕みたいな引きこもり気質でオタッキーな子たちのラブソングみたいになって面白いなって(笑)。「少年とミサイル」は、歌詞にも書いているんですけど、事務所に行く前に、駅のホームで男の子がすごくお母さんに怒られていて。「そんな怒らんでもええやん、かわいそうやん」というくらいに、人目をはばからずにめちゃくちゃに子どもを怒る親がたまにいますよね。子どもの嗚咽がすごくて、僕はそれを見ているのがしんどくて。でも、人さまのことなんで何も言えないしっていうモヤモヤを抱えつつ、目を逸らして電車に乗ったんです。それがすごく気持ち悪くて、その日のうちに作ったんです。
――しかも出来てから全然いじっていない感じですか。
内田:全然、いじってないです。盤に入れるためにCメロを足したりというのはありましたけど。
――弾き語りで聴くと、改めて歌が上手いなと。
内田:いやいやいや、恐縮です、それは(笑)。
――それと、内田さんってやっぱり内省的な人だなって。
内田:ははははは(笑)。

――あえてそういう曲を選んだことが、メッセージにもなっているのかなって思いました。
内田:バンドのイメージが、今まではあっけらかんとして、元気な感じだったと思うんですよ。でも、別に隠していたわけではないんですけど、バンドの方も今回のミニ・アルバムぐらいから「この人、もしかしてちょっとひねくれてるのかな?」というところを書くようにした。それは30歳を越えたっていうこともあるんですよ。今までは曲を書くときに10代、20代の子とか、「この曲はこういう人に届いてほしい」という狙いみたいなものを決めて書いていたんですけど、それを一切やめたんです。なぜかというと、10代の子に響く言葉を書けるのは10代の子だと思うし、20代前半に響く歌は、20代前半の子が書くべきだと思うんですよ。僕は、30代だから、30代にぶっ刺さる曲を書きたいなと思って、言葉を選び始めたんです。だから、15、6歳の子に深くわからない言葉もあると思うんですよ。それは若さを悪く言っているわけじゃなくて、僕もそうだったので。僕はそれぐらいの年齢のときに、ASIAN KUNG-FU GENERATIONやELLEGARDENの言葉に、全部は理解できなかったものの、カッコよさを感じていたんです。曲を書く上でそこに立ち返ったというか。でも、20代のときに30代に向けて書くというのは、違うんですよね。若いバンドがちょっと大人っぽいことを歌っているのは全然好きじゃなかったので。今やっと、逆のことができるようになった。30歳の僕が何を感じるかということだけを念頭に曲を書いた感じです。
――そういう曲作りをしてからのお客さんの反応っていかがですか。
内田:意外と僕らのお客さんって、同世代が多くて。そういう人たちはすごく共感してくれます。若い子らは、自分に置き換えられることは置き換えて聴いてくれていて。無理して自分で歌う対象を選ぶんじゃなくて、これでええんやなあって思いました。そうじゃないと僕が曲を書かせてもらっている意味はないっていうことに気付けたのが、今回のリリースで自分の中で一番の収穫だなって思います。
――曲作りだけじゃなく、歌い方なんかもリズミックを始めてからの10年間で変わりました?
内田:歌い方が変わったというのは、エンジニアさんに言われました。特にトレーニングしているわけでもなくて、こういう歌い方を意識している、ということは何一つ語れないんですけど(笑)。ただ自分でも思うのは、ここ1、2年で歌が自分のものになっている感覚はあるんです。声って身体なので、昨日と今日は違うし、ちょっとしたことでコンディションが変わったりするし。昔は、今よりもまだまだ自分の声に負けてたところがあるんです。今はどちらかというよりも、俺の方が偉いというか。「俺がおまえの声を出させてんねん」みたいな、「俺ひとつでおまえの出るも出ないも変わんねんぞ」っていう精神状態になっています。もう一人の戦ってる自分がいるというか。
――「ジョジョの奇妙な冒険」でいうところのスタンドみたいなもの?
内田:そうですね(笑)。そういう感覚があるんですよ。俺の精神次第で強くも弱くもなるという。「声に負けない」という気持ちが、この1、2年ですごくあります。
――声で言うと、「少年とミサイル」の歌い出しは、歌いまわしがちょっと違いますよね。これは意識的にそうしたんですか。
内田:「少年とミサイル」の世界は、時間帯が不特定なんです。朝なのか昼なのか、でも確実に夜ではなくて、夕方になるまでの時間帯のイメージなんです。そういう時間帯の、心が漲っている感じ、「今日はやるぞ」というガッツがある感じを出したくて、声の太さと出す場所を意識してちょっと変えたというのはあります。逆に「電影少女」は、ハイよりの薄いところを出しているというか、イメージで言うとサラサラしたシートで声をかぶせている感じです。「少年とミサイル」は、押しつけがましさはないように、でも心から歌っているという、ミドルとローを膨らませるイメージで歌っています。昔はそういうことができなかったんですけど、「こういう風に歌うぞ」というのは、今の方が明確にできるようになりました。
――そこが、聴いている人からすると、歌い方や表現の仕方が変わったという印象になっているのかもしれないですね。
内田:そうかもしれないですね。歌っている姿が見えやすくなってきたとは言ってもらえるようになりました。
◆インタビュー(2)へ
この記事の関連情報
【インタビュー】「DAM CHANNEL」20代目MCに森 香澄、サポートMCにチャンカワイが就任「プライベートな部分も引き出せたら」
2024年3月のDAM HOT!アーティストはアーバンギャルド、フジタカコら4組
【イベントレポート】<ビッグエコー35周年記念カラオケグランプリ>決勝大会が大盛況。応募4,061件の頂点決定
2024年2月のDAM HOT!アーティストはOHTORA、我生ら4組
2024年1月のDAM HOT!アーティストRKID'z、EINSHTEINら3組
2023年12月のDAM HOT!アーティストは学芸大青春、the paddlesら4組
【インタビュー】Rhythmic Toy World、通算100曲目の現在地に新局面と集大成「長い年月を経てここに辿り着いた」
Rhythmic Toy World、通算100曲目の最新曲はライフソング「命の絵」
2023年11月のDAM HOT!アーティストはACE COLLECTION、3markets[ ]ら4組