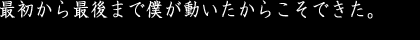
──逆に一番苦労したことは?
沖野:メールのやり取り。だって、参加を取り付けるだけで、最長2ヶ月かかった人もいますからね。コンセプトや条件、納品方法まで全部僕が一人でやったんですよ。しかも、やり取りは当然みんな英語。そうなると一日に対応できるのって、4人が限界なんですよね。その間、残りの16人はほったらかしになって、その4人とのやり取りも当然一日で終わるわけなくて。本当に大変でした。“全然、クリエイティヴちゃうし……”みたいな(笑)。
──でも、それをすることが重要だった、と。
沖野:レコード会社の人に任せずに自分の言葉で伝えたから、こういうプロジェクトが可能だったのかなとも思うんですよ。なんで、修也がメールしてこないのっていう不信感も生まれかねないし。やっぱり、最初から最後まで僕が動いたってことが、こういうプロジェクトを遂行する上では重要だったかな。変な話、トラック・メイカーから“締め切り明日だけど、ヴォーカルがまだ来てないよ”とかメールが来るんですよ(笑)。そのフォローもしつつ、ヴォーカリストにも“どんな感じ”って進行具合を確認して。今回は、そういう制作の管理とかディレクター/プロデューサー業務がいつにも増して煩雑でしたね。
──このアルバムの作り方は、藤原ヒロシさんの1stアルバム『Nothing Much Better』に近いものを感じました。彼は物事をミックスして、新たな価値観を作り出すという意味では非常にDJ的な人物だと思います。では、沖野さんの考えるDJとはどんなものなのでしょうか?
沖野:大きな柱が3つあるんですよ。ひとつは水先案内人というか、目利きですよね。自分の音楽のアーカイブの中からそのTPOに合わせて音楽を提案する。ホテル、映画館、それこそ、国によっても受ける音楽は全然違う。日本の中でもそうだし、時間一帯によっても違う。だから、状況に応じて自分の持っている知識の中から何を提案するか、このDJ的な感覚が僕のあらゆる活動に反映されていると思います。
──なるほど。
沖野:もうひとつは、その音楽がクラシックスとして生き残っていくものかを判断していくことだと思います。僕なんかは、新譜を聴いてもその作品が今後生き残って いくか、刹那的な快楽に応えるものか、長年のDJ活動を通して培ってきた識別能力というか、そういうもので分かってしまいますし。最後のひとつは踊らせ役ですよね。人をエンターテインさせることがDJの役割だと思います。ただ、3つ挙げたなかの1~2つ目は音楽以外にも適用できるDJ感覚だと思います。
< PREV | NEXT > | 