映画『一命』、三池崇史監督&坂本龍一インタビュー

 10月15日に公開となる映画『一命』、その“一命”を懸けた究極の人間ドラマに、またひとつの息吹を注いでいるのが、音楽を担当した坂本龍一のインスピレーションに満ちたサウンドだ。
10月15日に公開となる映画『一命』、その“一命”を懸けた究極の人間ドラマに、またひとつの息吹を注いでいるのが、音楽を担当した坂本龍一のインスピレーションに満ちたサウンドだ。◆映画『一命』予告編
ここでは、公開を記念し、三池崇史監督と坂本龍一の貴重なインタビューをお届けしよう。作品を作り上げていく両者のアーティスト性がいかに作品に影響を与えてきたのか、興味深いエピソードが溢れている。
──今回、坂本さんと一緒に仕事をすることになった経緯を教えて下さい。
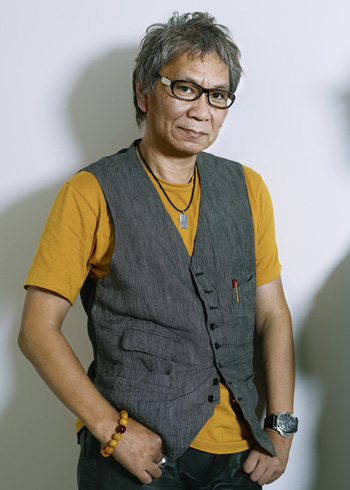 三池崇史監督:僕らの時代は、ラジオ文化が主で、何をする時もラジオを聴いていて、そのラジオの中で坂本さんが、映画音楽で世界で衝撃や話題を生んでいるのを知っていました。その時、ちょうど僕は、まだ助監督として仕事をしていたのですが、自分たちのやってることをずっとやり続けたことによって、プロデューサーのジェレミー・トーマスに出会い、坂本さんにも出会えました。そうして、僕は『一命』を作ることになり、坂本さんが音楽を作ってくれることになったんです。何だか夢のようだと思いましたし、「生きていれば色々あるもんだな」と感じました。映画を作り続けていくことで、そういう縁や力が生まれるんだと思います。
三池崇史監督:僕らの時代は、ラジオ文化が主で、何をする時もラジオを聴いていて、そのラジオの中で坂本さんが、映画音楽で世界で衝撃や話題を生んでいるのを知っていました。その時、ちょうど僕は、まだ助監督として仕事をしていたのですが、自分たちのやってることをずっとやり続けたことによって、プロデューサーのジェレミー・トーマスに出会い、坂本さんにも出会えました。そうして、僕は『一命』を作ることになり、坂本さんが音楽を作ってくれることになったんです。何だか夢のようだと思いましたし、「生きていれば色々あるもんだな」と感じました。映画を作り続けていくことで、そういう縁や力が生まれるんだと思います。──坂本さんが手がけられた日本映画の時代劇というと『御法度』がありましたが、今回『一命』のお話を受けて意識されたことはありましたか?
 坂本龍一:最初、ジェレミーに三池さんという監督がいるというのを教えてもらい、『十三人の刺客』を見せてもらったんですが、すごく力がある方だと思いました。以前に『御法度』の音楽もやりましたが、あの作品の舞台はお侍の時代設定であっても、時代劇というか、いわゆる“チャンバラ映画”ではないんですよね。今回の『一命』もそうなのですが、僕は“チャンバラ”を見せるような映画は向いてないので、やりやすかったです。それに、あまり時代劇という意識はありませんでした。こういった社会のルールと、それにそぐわない人間の事情っていうのは、誰にでも起こることだと思うので、そういう意味では普遍的な人間の話なんですよね。そういう部分でも僕としては、やりやすかったと思います。
坂本龍一:最初、ジェレミーに三池さんという監督がいるというのを教えてもらい、『十三人の刺客』を見せてもらったんですが、すごく力がある方だと思いました。以前に『御法度』の音楽もやりましたが、あの作品の舞台はお侍の時代設定であっても、時代劇というか、いわゆる“チャンバラ映画”ではないんですよね。今回の『一命』もそうなのですが、僕は“チャンバラ”を見せるような映画は向いてないので、やりやすかったです。それに、あまり時代劇という意識はありませんでした。こういった社会のルールと、それにそぐわない人間の事情っていうのは、誰にでも起こることだと思うので、そういう意味では普遍的な人間の話なんですよね。そういう部分でも僕としては、やりやすかったと思います。──今まで様々な映画音楽を手がけられてきていますが、坂本さんは映像を見ながら曲を作るというのをお伺いしました。今回も映像を見ながら作られたのでしょうか?
 坂本龍一:編集されている映像を順を追って見て作ることが出来たら一番いいんですが、条件が厳しく、そうもいかない時もありますね。ただ、映像を見ながら作っても、出来上がってみたら全然知らないシーンが入っていたり、全然違う映画になっているときもあります。でも、今回の『一命』に関しては、時間的にきつかったですが、既に編集が出来上がっていたので、とてもやりやすかったです。想像力で補わなければいけないということもありませんでした。
坂本龍一:編集されている映像を順を追って見て作ることが出来たら一番いいんですが、条件が厳しく、そうもいかない時もありますね。ただ、映像を見ながら作っても、出来上がってみたら全然知らないシーンが入っていたり、全然違う映画になっているときもあります。でも、今回の『一命』に関しては、時間的にきつかったですが、既に編集が出来上がっていたので、とてもやりやすかったです。想像力で補わなければいけないということもありませんでした。──今回の『一命』では、映像に助けられた部分やインスピレーションを受けた部分はありましたか?
 坂本龍一:基本的には映像からインスピレーションが得られないと作れないです。もっと言えば、その映画を愛することが出来ないと難しいです。映画音楽だけやっている人間だったら、その道の職人として一定レベルのものを出さなければいけないと思いますが、僕の場合はそこは少し違います。だから、「これをやりたいからやる」っていうくらい惚れ込まないと難しいです。この『一命』は、本当に一目惚れできる映画でした。
坂本龍一:基本的には映像からインスピレーションが得られないと作れないです。もっと言えば、その映画を愛することが出来ないと難しいです。映画音楽だけやっている人間だったら、その道の職人として一定レベルのものを出さなければいけないと思いますが、僕の場合はそこは少し違います。だから、「これをやりたいからやる」っていうくらい惚れ込まないと難しいです。この『一命』は、本当に一目惚れできる映画でした。──今回、カンヌ映画祭にも出品され、プロデューサーはジェレミー・トーマスさん、そして音楽には坂本龍一さんという方々と一緒に作品を作られましたが、三池監督ご自身、「勝負しよう」という意識はありましたか?
 三池崇史監督:基本的には、映画を作っていく中で“勝負”という感覚はないですね。以前、同じ原作の「異聞浪人記」が、『切腹』というタイトルで映画化されていますが、それと勝負するということになったら、「一体、誰がジャッジするんだ?」ってことになりますよね。その映画が存在したという事実からは逃れられないですし、むしろリスペクトしています。要は、得ることはあるけど、それ以外は何もないっていうことですよ。あとは、自分が面白いと思っているものが、映画の作り方からはじめ、文化の違いもあるジェレミー・トーマスというプロデューサーから見たらどう見えるのか、今の坂本さんからはどう見えるのかということなどは気になります。音楽だったら、坂本さんにどう映ったかということが、音楽という形で出てくるものだと思うので、とても興味がありますし、ワクワクしますね。
三池崇史監督:基本的には、映画を作っていく中で“勝負”という感覚はないですね。以前、同じ原作の「異聞浪人記」が、『切腹』というタイトルで映画化されていますが、それと勝負するということになったら、「一体、誰がジャッジするんだ?」ってことになりますよね。その映画が存在したという事実からは逃れられないですし、むしろリスペクトしています。要は、得ることはあるけど、それ以外は何もないっていうことですよ。あとは、自分が面白いと思っているものが、映画の作り方からはじめ、文化の違いもあるジェレミー・トーマスというプロデューサーから見たらどう見えるのか、今の坂本さんからはどう見えるのかということなどは気になります。音楽だったら、坂本さんにどう映ったかということが、音楽という形で出てくるものだと思うので、とても興味がありますし、ワクワクしますね。──なるほど。
 三池崇史監督:作品を作ることはもちろんですが、監督でいるっていうのは、最高の観客第1号でもあるということなんですよね。例えば、映画祭に行って、全く文化の違う人達と一緒に映画を見るというような特別な経験も出来るんです。そして、最終的に観客が映画を作るというのが現実なんですよ。同じ作品でも、上映する劇場や観客によって全く違う映画にもなるし、あるシーンの数秒の間でも、劇場によって、すごく緊張感に包まれたものになったり、単なる間延びしたものになったりするんです。やっぱり映画っていうのは、最後は劇場で仕上げられるんですね。あとは、最初に坂本さんに『一命』を見てもらって、「やっぱり、やらない」って言われたとしたらまずいけれど、その時点ではもう気に入られようとしても無理ですからね(笑)。でも、完成度とか、上手下手じゃなくて、その時点で今の僕らにしか出来ない匂いというのは出せたし、撮りながら感じたので、そういう部分が坂本さんにも伝わればいいなと思いました。ただ正座してる男のたたずまいなどにしても、今回3Dという特殊なカメラを使ってはいるんですが、映画的な切り取り方としては、オーソドックスで古めかしい手法でやっているんです。そもそも、食い詰めた浪人だとか、昔の人間を描くのに新しい手法で描いたらおかしいですよね。市川海老蔵をはじめ、僕自身撮っていて「日本の役者っていいな」という感触はあったので、そういう部分を坂本さんにも感じてもらって、“勝負”というよりかは、「前のめりになってもらえればいいな」という気持ちはありましたね。だから、勝負とかいうものとは、また次元が違う気がします。
三池崇史監督:作品を作ることはもちろんですが、監督でいるっていうのは、最高の観客第1号でもあるということなんですよね。例えば、映画祭に行って、全く文化の違う人達と一緒に映画を見るというような特別な経験も出来るんです。そして、最終的に観客が映画を作るというのが現実なんですよ。同じ作品でも、上映する劇場や観客によって全く違う映画にもなるし、あるシーンの数秒の間でも、劇場によって、すごく緊張感に包まれたものになったり、単なる間延びしたものになったりするんです。やっぱり映画っていうのは、最後は劇場で仕上げられるんですね。あとは、最初に坂本さんに『一命』を見てもらって、「やっぱり、やらない」って言われたとしたらまずいけれど、その時点ではもう気に入られようとしても無理ですからね(笑)。でも、完成度とか、上手下手じゃなくて、その時点で今の僕らにしか出来ない匂いというのは出せたし、撮りながら感じたので、そういう部分が坂本さんにも伝わればいいなと思いました。ただ正座してる男のたたずまいなどにしても、今回3Dという特殊なカメラを使ってはいるんですが、映画的な切り取り方としては、オーソドックスで古めかしい手法でやっているんです。そもそも、食い詰めた浪人だとか、昔の人間を描くのに新しい手法で描いたらおかしいですよね。市川海老蔵をはじめ、僕自身撮っていて「日本の役者っていいな」という感触はあったので、そういう部分を坂本さんにも感じてもらって、“勝負”というよりかは、「前のめりになってもらえればいいな」という気持ちはありましたね。だから、勝負とかいうものとは、また次元が違う気がします。 ──坂本さんの方は映像からインスピレーションを受けたということでしたが、三池監督は坂本さんの方から上がってきた音を聞かせてもらった時の印象はどうでしたか?
──坂本さんの方は映像からインスピレーションを受けたということでしたが、三池監督は坂本さんの方から上がってきた音を聞かせてもらった時の印象はどうでしたか?三池崇史監督:上がってきた音というより、プロセスの段階から見ていましたね。我々の場合、作品というのは、その映画を撮ってる現場の笑いや空気なんです。多くのキャストやスタッフが人生のある時間をそこで過ごすので、撮る方も撮られる方もその空気や時間を楽しんでいるかどうかが大事。その結果生まれるのが映画ならば、楽しい作業になるじゃないですか。例えば、自分たちは全然面白くなくて、苦しみながら作った映画が名作になると、「映画を作るためには苦しまなくちゃいけないのか?」ということになってしまう。もちろん真剣にやっているし、大変は大変なんですが、やはりエンターテイメントなので、「作る側が楽しんでいないと」という思いは常にあります。だから、どう音楽が生まれ、作られているのかなど、すごく興味があったので片隅からずっと見ていました(笑)。すごく刺激になりましたね。集中力もすごいですし、芸術家として作るという部分と、プロとして仕上げていくという両面が成立している現場はそうそう見られないです。出来上がった音楽を初めて聴くと、普通はスタッフやミキサー達は、映画の中でどう使うかを考えるんですが、今回はその作業が不要でした。最初の音をそこに置くと、そのまま自然と映像に繋がるようだったので、ダビングの作業なども今回は特殊な世界でした。非常に楽しみながら出来ましたね。
 ──今回、三池監督と一緒にお仕事をされてどんな印象でしたか?
──今回、三池監督と一緒にお仕事をされてどんな印象でしたか?坂本龍一:印象的だったのは、独特の感覚がある人で、タイミングにすごくこだわるんですよね。あとは、僕もそうなんですが、教科書に書いてあるような当たり前なことはやりたくないタイプだと思いました。そのあたり前じゃないことをしている自分が楽しいんですよね。だから、打ち合わせをしていても、「普通はこうだから外してみましょうか」「今回はあえて普通にやってみましょうか」など、三池さんは、そういった掛け合いが出来る監督なので楽しかったですね。
──その「外す」というのは、確信的なのでしょうか?それとも偶然の産物なのでしょうか?
 坂本龍一:偶然はないですね。1秒の何分の一というところで確信を持ってやっていかなくてはダメな世界なので。
坂本龍一:偶然はないですね。1秒の何分の一というところで確信を持ってやっていかなくてはダメな世界なので。三池崇史監督:微妙なタイミングの違いなど、僕の耳ではとうてい分からないことがたくさんありますよ。あとは、そのシーンを見るために5~6秒前からリプレイするのですが、その前にも何かしらの音は鳴ってるんですよね。もっと言うと、映画が始まって1時間半の時点のシーンの場合は、1時間半前の音を聞いて、そのままスッと入れる音にするんです。普通はそのシーンだけで判断をしがちですが、その前に風や雨の音があったら、「スッと入れるのはこのタイミングだ」というのが、直感的に分からないといけないんですよね。坂本さんが確信と言われたのは、シーンを遡って状況を見た上で、直感で「このタイミングだ」というものがあるということだと思います。これは映画音楽のいいところと不自由なところでもあると思いますが、例えば、映画音楽を作りつつ、音響を全部やる監督だとしたら、これほどやっかいな仕事はないですよね。それらを避けて、作曲に集中する。そうして出来上がったものを、預けられるので、僕らはそれを守りながら作業をするんですよね。それがまた、面白いですし、僕やスタジオの人間も楽しみながらやっていました。
 ──映画が完成した時のご感想は?
──映画が完成した時のご感想は?三池崇史監督:いつもそうなんですが、出来上がっての感想は、「いいスタートが切れたな」という気持ちですね。公開が始まるのはこれからですが、作り上げたことによってゴールとしたというよりも、「今始まった」という感覚です。
坂本龍一:映画はお客さんに観ていただいて初めて完成するものですし、音楽も同じく聴いてもらって初めて音楽になると思うのです。だから、まず観ていただいて、何かしら感じていただきたいですね。海老蔵さんを筆頭とする役者陣のパフォーマンスも力強く、素晴らしいです。僕自身もこの作品に、すごくインスピレーションを受けたので、是非観ていただきたいです。
映画『一命』
 貧しくとも、愛する人と共に生きることを願い、武家社会に立ち向かった二人の侍の生き様に、心が震える感動作。1958年に発表され、1968年には映画「切腹」とし世界に名を轟かせた伝説の物語「異聞浪人記」が、今、50年余の時を経て、再び世界に衝撃を巻き起こす。主演に、比類なき存在感と天賦の才で、他を圧倒する歌舞伎俳優・市川海老蔵と、繊細な演技に定評のある若き実力派俳優・瑛太。企画・プロデューサーに「おくりびと」「13人の刺客」の中沢敏明、「戦場のメリークリスマス」「ラスト・エンペラー」のジェレミー・トーマス。鬼才・三池崇史監督が、時代劇初の3D作品として切り開いた新境地。名実ともに世界基準、最上級にして最強の製作陣が集結、“一命”を懸けた究極の人間ドラマが誕生した。
貧しくとも、愛する人と共に生きることを願い、武家社会に立ち向かった二人の侍の生き様に、心が震える感動作。1958年に発表され、1968年には映画「切腹」とし世界に名を轟かせた伝説の物語「異聞浪人記」が、今、50年余の時を経て、再び世界に衝撃を巻き起こす。主演に、比類なき存在感と天賦の才で、他を圧倒する歌舞伎俳優・市川海老蔵と、繊細な演技に定評のある若き実力派俳優・瑛太。企画・プロデューサーに「おくりびと」「13人の刺客」の中沢敏明、「戦場のメリークリスマス」「ラスト・エンペラー」のジェレミー・トーマス。鬼才・三池崇史監督が、時代劇初の3D作品として切り開いた新境地。名実ともに世界基準、最上級にして最強の製作陣が集結、“一命”を懸けた究極の人間ドラマが誕生した。海外版タイトル:HARA-KIRI: Death of a Samurai
企画・プロデューサー:中沢敏明、ジェレミー・トーマス
原作:滝口康彦「異聞浪人記」
監督:三池崇史
脚本:山岸きくみ
出演:市川海老蔵、瑛太、役所広司、満島ひかり、他
制作プロダクション:セディックインターナショナル
配給:松竹
公開:2011年10月
http://www.ichimei.jp/
◆BARKS 映画チャンネル
この記事の関連情報
坂本龍一を聴いて奏でる。『out of noise - R』発売記念 世界最速先行試聴会開催
坂本龍一、最後のピアノソロコンサート作品『Opus』配信リリース
NHKスペシャル『Last Days 坂本龍一 最期の日々』放送
東北ユースオーケストラと坂本龍一によるコンサート作品集発売
坂本龍一、毎月28日の月命日に公式T-shirts販売
坂本龍一の誕生日に一夜限りのスペシャルイベント開催
<AMBIENT KYOTO 2023>、撮り下ろしスペシャルムービーを11月20日(月)より期間限定公開&コラボイベント<ACTIONS in AMBIENT KYOTO>12月10日(日)開催
坂本龍一、最初で最後の長編コンサート映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』東京国際映画祭での上映決定
坂本龍一と高谷史郎のコラボ作品『TIME』日本初公演の詳細発表