-異種格闘技対談-Ring【round2】:第2回/川島道行(BOOM BOOM SATELLITES/Vo & Gt)
-異種格闘対談-Ring【round2】第2回
ゲスト 川島道行 BOOM BOOM SATELLITES/Vo & Gt 逹瑯 ムック/Vo
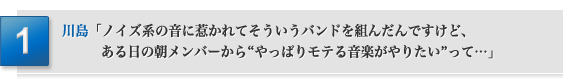
逹瑯: 緊張してます(笑)。
川島: いやいや(笑)。その倍以上緊張してます(笑)。よろしくお願いします。
逹瑯: いや。もぉ、こちらこそです。

逹瑯: まったくの初対面。だから、もぉ、緊張しまくりなので、すいません(笑)。1月27日にリリースされた初のベスト『19972007』を聴かせてもらったんですよ。ものすごくカッコ良くて、改めてびっくりしちゃったんですけど、1997年から2007年までのベストなんですよね?
川島: そうですね、ベストは初なので。
逹瑯: 1997年っていったら、ウチらがムックを結成した年なんですよ。もぉね、そこでもびっくりですよ。ウチらを中心に話してしまって申し訳ないんですけど、最近ウチらのシーンでは、4つ打ちとかダンス・ミュージックとか、エレクトロニカを取り入れた楽曲が目立つようになってきたんです。でも、BOOM BOOM SATELLITESは、1997年の頃からバリバリやってたんですもんね。ホント、ダンス・ミュージックとロックを融合させた日本のアーティストのパイオニアなんだなって、改めて感じましたね。それもあって、そんな人と対談なんて、いいの? すいません。的な緊張で(笑)。
逹瑯: あははは。緊張しすぎてまともに見れないっていうね(笑)。
川島: あはははは。
逹瑯: BOOM BOOM SATELLITESは、海外での活動の方がメインなんですか?

川島: はい。そうですね。ベルギーのR&Sレコードからアルバムが出てるんですけど。その前に、田中フミヤさんっていうDJの方がやられている“とれまレコード”のサブレーベルだったUNTITLE RECORESっていうところから出したコンピレーション・アルバムに、1曲入れてもらったのが音源化した初でしたね。でも、そのときはまだどことも契約を結んでいなかったんで、ニンジャチューン(UKクラブシーンで人気のレーベル)とか、いろんなレーベルにデモテープとか送ってたんですけど。そんなときに、R&Sの方から興味があるっていう話が来て、サインをしたのがきっかけだったんです。
逹瑯: じゃぁ、出だしがもう海外なんですか?
川島: そうですね、まぁ、同時期って感じでしたけど、ちゃんとした形での最初のリリースは海外でしたね。
逹瑯: すごいですね。今、日本のバンドもたくさん海外に行ってたりしますけど、俺たちのシーンって、アニメとか日本の文化のひとつとして、ニーズがあるんですよ。流行ものに乗って海外に行ったって感じの行き方が最初のとっかかりだったんで、BOOM BOOM SATELLITESとはまったく違うなって。BOOM BOOM SATELLITESは自らの個性で、道を切り開いてきたって感じしますもんね。それがすごいなって思う。流行とか関係なく、音楽自体を大きく評価されてるっていう感じが、本物だなって思いますね。いや、なんか、俺がいうのも、おこがましいんですけど(笑)。ムックも最近、エレクトロとかダンス・ミュージックを取り入れだしてきてるんですけど、最初にいききった4つ打ちをやったのは、今から3年くらい前になるのかな? 「ファズ」っていうシングル曲があるんですけど、その曲で初めて冒険した感じだったんですよ。
川島: あぁ、なるほど。デッド・オア・アライヴ。
逹瑯: そうそう。ラジオかなんかで流れてたのをたまたま聴いて、カッコイイな、なんてバンドかな? って思ったくらいの知識しかなかったんですよ。だから、どんな人たちなのか、まったくヴィジュアルも知らなかったんで、「ファズ」のPVを撮ることになったときは、曲調的に、今回はまったくメイク無しな感じでいいんじゃない? って感覚だったんですけど、ディレクターに、“いや、この曲ではガッツリメイクして押し出した方がいい!”っていわれて。正直、“ん? 4つ打ちでガッツリメイク???”ってイメージがつかなかったんですけど、デッド・オア・アライヴのPVとかをyou tubeで見て、“なるほど! こっち系のこといってんのか! カッコイイじゃん!”って思ったんですよ。ウチらにとっては、逆にすごく新鮮だったというか。普段は、ヴィジュアル系のメイクっていうんじゃないんですけど、ウチらは目の周りを黒く塗る感じの、ちょっとゴス系のメイクしてるんですけどね。
川島: あぁ、はいはい。なるほど。
川島: 僕もバンド始めたのは中学生くらいの頃だったんですよ。最初はベースを買って、ベースやってたんですけどね。当時はBOOWYとかラフィンノーズとか、あとはヘヴィメタルとか、すごい流行ってましたね。
逹瑯: 俺、兄ちゃんが2人いるんですけど、上の兄ちゃんが8歳上で、その兄ちゃんが文化祭でバンドやってたときの映像見ると、BUCK-TICKとかカヴァーしてるんですよね。その時代よりもちょっと後くらいってことですよね。
川島: そうですね。BUCK-TICKは、もうちょっと後だったかな。それこそ、周りがBOOWYとかラフィンノーズとかに夢中になってた頃から、僕はそういう音楽ではなく、ニュー・ウェイヴと呼ばれる音楽にすごく惹かれて、キリング・ジョークとか、オーストラリアのSPKっていう鉄板叩いたりするようなノイズ系の音に惹かれてたんです。それで、自分もそういうバンドをやりたくて、バンドを組んだんですけど、ある日の日曜日の朝に、メンバーから、“そういう音楽やりたくないんだよね……”っていわれて……。
逹瑯: あははははは(大爆笑)。
川島: “どうしても、やっぱり、モテるような音楽がやりたいんだけど……”って。
逹瑯: あはははは。ものすごい面白いんですけど、その話(笑)! でも、たしかに、他のメンバーの気持ちは俺、すっげぇ解りますよ(笑)。だって、中学とか高校の頃ですよね? そんな難しいアングラな音楽より、やっぱ最初は“モテたい!”ってとこからいくと思いますもん。いやぁ、他のメンバー、間違ってないと思いますね(笑)。
川島: うん、まぁね(笑)。
逹瑯: あははは。でも、珍しいっすよね、川島さんは、そっちにいかず、最初からそういう難しい音楽やろうと思ったっていうのも。
川島: まぁ、でも僕もカッコつけてたと思うんですよ。田舎で育ってるんで、アートなモノとか、人とは違ったモノっていうのをやりたかったっていう。あまり人に理解を求めない音楽というかね。そういうところに魅せられてたと思うんですよ。人との共通項を敢えて避けるような。それと、若いですから、死というモノに対して、漠然とした憧れがあったというか。化粧とかもしてたんですよ、最初の頃は。
逹瑯: へぇ~!

この記事の関連情報
-異種格闘技対談-Ring【round2】特別編/櫻井敦司(BUCK-TICK)【PHOTO】
-異種格闘技対談-Ring【round2】特別編/櫻井敦司(BUCK-TICK)
-異種格闘技対談-Ring【round2】第24回/INORAN【PHOTO】
-異種格闘技対談-Ring【round2】第24回/INORAN
-異種格闘技対談-Ring【round2】第23回/綾小路翔(氣志團)【PHOTO】
-異種格闘技対談-Ring【round2】第23回/綾小路翔(氣志團)
-異種格闘技対談-Ring【round2】第22回/ホリエアツシ(ent、ストレイテナー)【PHOTO】
-異種格闘技対談-Ring【round2】第22回/ホリエアツシ(ent、ストレイテナー)
-異種格闘技対談-Ring【round2】第21回/しずる【PHOTO】